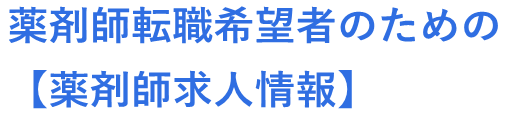本ページはプロモーションが含まれています
調剤薬局で働く場合の仕事内容
日本調剤やアインファーマシーズなど調剤薬局での仕事は、主に隣接している大きな病院や診療科が処方する、処方せんの調剤業務が主な仕事になります。
その他には患者さんごとの薬歴管理や、服薬指導(インフォームド・コンセント)、医薬品の管理や供給などの業務があります。
電子薬歴の普及や調剤の機械化、無菌調剤の対応など、新しいシステムに早く慣れる必要もあります。
調剤薬局での薬剤師の仕事は、どんな薬を処方するか、どんな服薬指導(インフォームド・コンセント)が必要になるのかで具体的な内容が変わってくることがあります。
近場にある病院や診療科にどんな患者さんが訪れることが多いかで、内容が変わってくるのです。
たとえば耳鼻科に近い調剤薬局の場合、中には耳が悪いという方も訪れるでしょう。
耳が悪い方にどんな服薬指導(インフォームド・コンセント)を行うのか、その薬局の指針に従って特別な対応が必要になることも多いでしょう。
また小児科が近い場所では、子どもとご両親向けの特別な対応も必要なはずです。

症状が重い患者さんが多い地域では、調剤にもスピード感を求められることも多いはずです。
患者さんの日頃の暮らしぶりを知るために、患者さんとのコミュニケーションを密にとらなければならない場面もあります。
また近隣の病院や診療科から薬についての問い合わせが入り、それについての回答や対応策を練らなければならないこともあります。
逆に医師の処方した薬の処方せんに疑義があると感じたら、疑義照会をしたりすることもあります。
調剤薬局でどんな仕事を求められるのかは、その薬局周辺にある病院や診療科でどんな患者を診ているのかで変わってきます。
調剤薬局でどんな仕事が必要なのかは、周囲や実際の現場を自分の目で見て確認するのが大切だといえます。
薬局によっては、在宅医療を推進している場合もあります。
在宅医療での薬剤師の仕事は、調剤業務やそれを患者さんのお宅へ直接届ける事の他に、患者さんの残薬を整理したり、薬剤の保管方法や服薬方法をご本人や家族、ヘルパーさんなど介護スタッフへ指導したりすることも仕事のひとつになります。
特に在宅医療はこれからますます重要視されている仕事で、取り組む薬局が増えていくとされている内容です。
今は在宅医療を取り扱っていないところでも、後々求められることがあるかもしれません。
各団体で開催されている勉強会や研修に参加し、いつでも対応できるよう準備を整えておくことは必要かもしれません。
かかりつけ薬剤師が新設
2016年11月初旬位に新聞と一緒に「かかりつけ薬剤師の解説と利用案内」の折り込みチラシが入っているのを始めて見ました。
市販薬も含めた患者の服薬状況を一元的に管理するのが「かかりつけ薬剤師」です。かかりつけ薬剤師のイメージはプライベートジムで専属トレーナーとのマンツーマンレッスンがわかりやすかもしれません。
2016年2月10日の中央社会保険医療協議会の答申(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html)で診療報酬の改定とともに新設が答申されました。(89ページにかかりつけ薬剤師に関しての記載があります。)
かかりつけ薬剤師が服薬指導などを行った場合には通常よりも多い薬剤師指導料になります。
かかりつけ薬剤師の主な要件
- 薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
- 同一の保険薬局に32時間以上勤務しているとともにその保険薬局に半年以上在籍している事
- 研修認定を取得している事
- 医療に係る地域活動の取り組みに参画していること
薬剤師の資格を取得したらそれで終わりではありません。日々の知識の積み重ねが必要です。
かかりつけ薬剤師になるための条件の一つに「研修認定薬剤師」の資格を取得する必要があります。
研修認定薬剤師は取得と更新に一定の単位が必要です。新規は40単位、更新は30単位。
しかも更新に必要な30単位は3年以内に取得する必要があります。しかも1年間にまとめて30単位取得するするのは認められず、1年の期間に最低5単位以上取得していく必要があるのです。
- 1年目が5単位
- 2年目が10単位
なら3年目は15単位の取得が必要になる計算です。
かかりつけ薬剤師の主な業務
- 患者の理解に応じた適切な服薬指導
- おくすり手帳などを用いて指導の内容を記載
- 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握する
- 一般用医薬品や健康食品なども全て把握する
- 患者から24時間体制で相談に応じる
- 患者に薬剤を入れる袋を配布する
開局時間外など止むを得ない場合にはあらかじめ患者の同意を得た上で別の代替薬剤師が相談に応じる旨を説明しその薬剤師の連絡先を患者に伝える必要があります。
高齢者の患者は多くの薬剤を同時に服用している場合が多いです。
そのような患者にとっては服薬状況を市販薬も含め健康食品も全て把握してくれるかかりつけ薬剤師が存在するととても心強いものです。
指名は患者本人が行うので薬剤に関する深い知識はもちろんフレンドリーな対応など患者に喜ばれる対応を心がけると良いでしょう。